入選一覧・講評
CHOSEN
公益財団法人沖縄県文化振興会が主催する「第20回おきなわ文学賞」において、全6部門合計247作品の応募の中から、40作品38名の受賞者が決定しました。
一席6名、二席6名、佳作23名、奨励賞5名です(うち2名は2部門で受賞)。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
下記ボタンをクリックすると該当エリアへ移動します。
小説部門

〔 入賞作品 〕
| 賞 | 作品名 | 作者名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 一席 沖縄県知事賞 ※順不同 | したたる手汗は拭けずとも | 翠彩 えのぐ | 那覇市 |
| 一席 沖縄県知事賞 | タヒーボ | 島袋 克 | うるま市 |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 | ー | ー | ー |
| 佳作 | 松ちゃんの誠 | 仲村渠 ハツ | 宜野湾市 |
| 佳作 | 乳歯が抜けた日 | 石川 みもり | 浦添市 |
| 佳作 | ゆきうみの子 | 梓弓 | 豊見城市 |
| 佳作 | 神様のジャンク品 | 黒ひょう | 読谷村 |

〔 選考委員・講評 〕

1949年沖縄県大宜味村生まれ。
元琉球大学教授、詩人、作家。
受賞歴に沖縄タイムス芸術選奨(評論)奨励賞、具志川市文学賞、沖縄市戯曲大賞、文の京文芸賞、九州芸術祭文学賞佳作、山之口貘賞、沖縄タイムス芸術選奨(小説)大賞、やまなし文学賞佳作、さきがけ文学賞など。
文学の可能性を追求した豊かな作品世界
今回はレベルの高い応募作品が多かった。文学の可能性を追求した豊かな作品世界が展開され、小説でしか描けない世界を作り上げている。このことをたのもしく思った。
入選作品は六編、第一席は甲乙つけがたく、二作品の同時受賞となった。受賞作品「したたる汗は拭けずとも」(翠彩えのぐ)は、心因性の手掌多汗症を患った主人公がネパール人留学生らとの出会いによって、「何のために生きるのか」という問いへの答えを得るまでの物語だ。鮮明なメッセージを国境を越えた交流から得るところに工夫があり広がりと深さがあった。今日のグローバル社会をも射程に入れた作品で整った文体も高く評価された。
もう一つの受賞作品「タヒーボ」にも感心した。ボリビア移民の辛苦な人生を浮かび上がらせた作品だ。現地の風物を取り込んだ描写は具体的で臨場感がある。人物の造型も見事で沖縄県民のもう一つの戦後史だと思われた。作品の彼方に立ち上がるいくつもの物語があり、小説としての面白さもある。出来映えに圧倒された。
佳作の四編も力のある作家たちが独自の世界を作り上げていた。「松ちゃんの誠」は三人の仲良しおばさんたちが、「センソウーしちゃならん」と路上ライブをする。この三人の家庭の事情などを紹介しながら沖縄社会や沖縄の課題を沖縄目線で見事に描きあげた作品だ。「乳歯が抜けた日」は小児虐待、育児放棄という現代の課題を作品化した。表現が具体的でリアリティがある。温かいエンディングも好ましかった。「ゆきうみの子」は中卒で製塩工場で働き始めた「僕」と高校へ進学した若葉との爽やかな恋愛物語だ。「僕」の揺れ動く心理がよく描かれている。文章にも一貫したリズムがあって独自の文体を作り出していた。「神様のジャンク品」は、近未来の社会が舞台だ。「私の名前は『コウ』。人型ロボットとして(中略)働いている」で始まるユニークな設定だ。人間とロボットを登場させ人間社会の仕組みや人間関係の在り方を批判した。この目論見は成功しているように思う。対立の構図も効果的で、伏線の巡らしかたもとても巧みである。作者の構想力と想像力に高い評価を与えたい。応募者諸氏のさらなる飛躍を期待したい。

那覇市生まれ、那覇高校、名古屋瑞穂短期大学を卒業後、栄養士として、務めつつ、保育士の資格をとり、自ら保育園を設立。保育事業に携わる一方、創作活動も行う。第10回琉球新報短編小説賞「イヤリング」佳作、第15回九州芸術祭文学賞「束の間の夏」地区優秀作、そのほか、新聞や業界誌などでコラム、エッセイ等を執筆。沖縄エッセイストクラブ会員。「亜熱帯」同人。
社会福祉法人あおぞら福祉会あおぞら保育園理事長兼園長。
一席 【したたる手汗は拭けずとも】
家が貧乏のため、役人となって楽して生きていきたいと、大学生活のほとんどを勉強に捧げたのに、公務員試験は不合格が続き、一年近くも自宅に引きこもっていた主人公。社会復帰をめざし不動産会社に勤めるが、少しずつ先が見えてきた矢先に大きなトラブルが発生してしまう。が、仕事を通して出会ったネパール料理人スベディの逞しい生き方や、不動産会社の社長夫妻の支えで、力強く生きて行こうと決意する姿が清々しい。アジアからの留学生の実情もリアリティがある。作者は毎年のように応募を続け、今回とうとう一席の座を射止めた。新たな作品で更なる挑戦をめざしていただきたい。
一席 【タヒーボ】
コロニア・オキナワ入植50周年の取材でボリビアを訪れた農協職員の徳元には、もう一つ目的があった。ボリビア人暴行致死事件の容疑者となり開拓地から失踪した叔父勇吉の消息を探すことだった。運転手兼通訳として同行する日系農協職員の岡田との会話を通して、勇吉の人柄や徳元の半生が浮かび上がる構成が良い。移住地の情景やタヒーボの描写も秀逸。が、勇吉の娘にたどり着くまでの展開がスムーズ過ぎる。こんなに早くみつかるのなら、なぜ沖縄にいる勇吉の姉(徳元の母)は、もっと本気で行方を探そうとしなかったのだろうか。勇吉の無実を信じていたはずなのに…。人間の生き方を考えさせる小説。
佳作 【松ちゃんの誠】
清掃の仕事をしている松ちゃんと節ちゃんと真鶴の3人は共に60代、模合仲間である。ある日、松ちゃんはネットで戦争まであと10年という記事を見つけた。それを骨の髄まで戦争ウトゥルー(恐がり)が浸みこんでいる真鶴に話したところから話が急展開する。真鶴が高校前のバス停で高校生たちに路上ライブを始めるというのだ。それも離婚覚悟で。登場人物がたくさん出てくるが、会話を通してそれぞれの性格がよくわかるし、味がある。ラストの緊迫感と「警官が来たぞ」が効果的。安里屋ユンタの替え歌の歌詞も良い。「戦争シチェーナランド-、サーユイユイ」。作者の危機感がひしひしと伝わってくる。
佳作 【ゆきうみの子】
中卒の櫂は一人暮らしをしながら塩工場で働いている。月に2度、銀行で母親からの4万円の振り込みを確認して金を下ろす。母親は櫂の中学の卒業式にも来なかった。父親も生きているのか死んでいるのかもわからない。そんな櫂にはなにかと面倒をみてくれる職場の先輩や好意を寄せてくれる中学の同級生がいて…。塩工場の描写が新鮮。海水から塩を作る工程での塩の変化が美しく書けている。
今回は応募総数30作品。年齢は17歳から80歳と幅広く、女性14人の応募はこれまでで最多ではないだろうか。レベルの高い作品が並び、選考委員の意見も活発で、結果1席が2名ということになった。書き続けているといつかヒットが出ると信じて、来年もぜひ多くの方が応募してほしいと願っている。

1981年広島県三原市生まれ。沖縄国際大学教授(沖縄・日本近現代文学)。
2000年~2008年まで琉球大学および琉球大学大学院で学ぶ。東京大学大学院博士課程を経て2016年に沖縄国際大学総合文化学部に着任。
著書に『出来事の残響ー原爆文学と沖縄文学』(インパクト出版会)。
本年度は一席に二作品、佳作に四作品が選ばれた。ともに一席となった「タヒーボ」と「したたる手汗は拭けずとも」は、実に対照的な趣を備えて一席を彩っている。半世紀前に沖縄からボリビアに移民していった人々の歩みを円熟した筆力で綴った作品と、グローバル化していく沖縄において従来の日本社会の価値基準から逃れようともがく若い世代を描いた作品の拮抗である。
「タヒーボ」は、徳元という取材者が半世紀前に沖縄からボリビアに移民した新垣盛徳、高良勇吉を追いかける物語である。ボリビア移民の境遇やコロニアの変遷、そして盛徳と勇吉の間に秘められた事件の解明と、実に読ませる展開である。南米の自然の描写も卓越であった。
「したたる手汗は拭けずとも」は、公務員試験の不合格が続いて心身ともに不安定な状態に陥った主人公が知り合いの不動産屋で働くこととなり、ネパールから留学や就労のために沖縄にやってきた若者たちとの関わりを通して変化していく、成長と回復の物語であった。「死ぬほど好きなもの」がなければいけないのか、という主人公の問いと苦しみに自らを重ねる若い読者も多いのではないだろうか。
佳作には、「松ちゃんの誠」、「乳歯が抜けた日」、「ゆきうみの子」、「神様のジャンク品」の四作が選ばれた。「松ちゃんの誠」はまさに沖縄の現実を切り取ったような作品である。「センソーしちぇならん」の声をささやかに響かせることに伴う決意と、その決意を軽く見て押さえつけようとする、これまた沖縄社会に内在する圧力との拮抗が描かれており、心を引かれた。
「乳歯が抜けた日」は、乳歯やランドセルといったモチーフを実に巧みに用い、ネグレクトにあっていた義妹の娘を引き取ることを決意した「私」が、義妹の娘との関係を築いていくまでが描かれている。確かな筆力に支えられた作品だが、義妹の娘より幼い実の娘も育てている主人公の葛藤が一応の落ち着きを見せ、義妹の娘にとって引き取られた家族が新たな居場所になるまでには「一ヶ月」という作品内の設定よりはるかに長い時間が必要であるようにも感じた。せっかくの構想がリアリティを失うものにならないよう、注意を払ってもらいたい。
「ゆきうみの子」は、中学校卒業後に製塩場で働く主人公を取り巻く状況を描いた作品である。ひたむきに仕事に向き合う主人公は、周囲の支えやかつての同級生とうまく向き合うことができずにいるが、次第に変化していく。製塩場という白の世界のイメージは美しく、描写にも引き込まれる。主要な登場人物一人ひとりがいま少し深まりのあるかたちで書けていると、より優れた作品になったように思う。
「神様のジャンク品」は、人型ロボットと鬱病で休職していた男性との交流を描く。構成やラストシーンの描写は巧みであるが、語りの主体がロボットであるということにまず面くらってしまった。ロボットが自発的に語り起こすとはどのようなシュチュエーションなのか、そのことに関する掘り下げがほしかったと思う。ロボットが「私」に基づく語りを展開するとき、もはやその存在はロボットとは言えないのではないか。
今年度は、全体として粒揃いの作品を読むことができ、大変楽しく、難しい審査をさせていただいた。惜しくも選外となったが、「画面越しの溝」という作品には大きな可能性を感じた。今後もぜひ、おきなわ文学賞にすばらしい作品をお寄せいただきたい。
随筆部門

〔 入賞作品 〕
| 賞 | 作品名 | 作者名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 一席 沖縄県知事賞 | 書店員の誕生日 | 成田 すず | 那覇市 |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 | 「ろんぐ」と「いらきむぬ」 | 上間 さちよ | 那覇市 |
| 佳作 | ウチナ―グチと男の子 | 諸見里 杉子 | 那覇市 |
| 佳作 | 奇跡のラブレター | 平良 政勝 | 浦添市 |
| 佳作 | 父の手帳 | 長嶺 弘美 | 糸満市 |
| 佳作 | 首里城に魅せられて | 照喜名 一 | 那覇市 |
| 奨励賞 | 星を語る人 | 佐々木 向日葵 | 北谷町 |

〔 選考委員・講評 〕

1962年生まれ。週刊レキオ、季刊「カラカラ」、「おきなわ食べる通信」などの編集長を務めたのち、現在は泡盛居酒屋店主。琉球泡盛倶楽部会長。
琉球新報紙「落ち穂」執筆中(2023年7月〜12月)。
第1席の「書店員の誕生日」の作者は、文章を書き慣れていると感じた。書店員になってわずか半年後に、輸送船が座礁して積荷の本が届かないという大事件に巻き込まれ、その対応に的確に迅速に動く先輩職員とともに事後処理をこなしていく。書店の書物のほとんどが船便で届く沖縄の特殊事情と、書店員しか体験できない輸送船座礁事故のときの体験談がうまくまとめられていた。個人的には、書き慣れているからこそ文章が落ち着き過ぎていて、その時々に揺れ動いたであろう個人の感情や思いが抑えられているように感じる。この方のもっとはっちゃけた随筆も読んでみたい。
第2席の「ろんぐといらきむぬ」も素晴らしい。父親の初七日の法事料理に母親の指導のもと取り組む5人姉妹。料理の中には父母の郷土の八重山料理が2品あり、それが姉妹にとっては初めての「ろんぐ」と「いらきむぬ」だった。これらはその後の父親の法要ごとに仏壇に供えられ、母と5人姉妹一緒に作った。その母が肺を患い、本人も余生の短さを感じ始めてからの家族を描いた部分が良い。何気ない会話の中に、互いに思い合う母娘の気持ちが伝わる。そして、母の死後、今度は姉妹だけで作る「ろんぐ」と「いらきむぬ」が、両親の死後も姉妹を結ぶ母の味となる。締め方もうまい。
佳作の「ウチナーグチと男の子」は、題材が面白い。方言しかしゃべらない中学生時代のクラスメイトという素晴らしい核があるのだから、最後をさらに工夫したらさらに良い作品になったと思う。
同じく佳作の「奇跡のラブレター」は、定年を迎える職場の先輩の年金請求をするために、先輩が戦前、首里の郵便局で働いていた証拠を探す女性職員の話。そこで現れたのが、先輩の初恋の相手で、彼の過去を知る同級生。彼女を手掛かりに先輩の職歴の証言者をさらに探していく。その独特の体験談がよくまとめられている。
同じく佳作の「父の手帳」、「首里城に魅せられて」は、やや説明的、平板的に感じた。自分が選んだテーマの、何が面白いと感じたのかを、もっと突き詰めると違うエピソードが浮かんだり、より気持ちを伝えられる文章が生まれたりするのではないか、と思う。
また、今回は13歳の中学生の応募もあった。上位受賞とはならなかったが、奨励賞を機に、これからも自分のそのときどきの気持ちを文章にして人に伝えることに楽しさを見つけてほしい。

1954年那覇市に生まれる。沖縄県立那覇高等学校(27期)卒業、九州芸術工科大学(7期)環境設計学科卒業。設計業務とグラフィックデザイン等を経て趣味で執筆を始める。2003年「第1回祭り街道文学大賞」にて『女人囃子がきこえる』で大賞受賞。2010年「第19回ふくふく童話大賞」にて「クモッチの巣」で大賞受賞。著書に『花水木~四姉妹の影を追って~』、『ファイナルジェネレーション~記憶と記録の復帰前~』など。現在は市井の人々のオーラルヒストリーを聴き取り、個人史として残す仕事に取り組む。
2004年より沖縄エッセイスト・クラブ会員。
2020年10月より同クラブ編集委員長。
面白いもので二人の選考委員の選出作品が被らないことは多々あるのだが、今回はひとつだけしか被らなかった。つまりバラバラである。その唯一、一致した作品を一席とした。選考後に知ったのだが、一席の方は三作品出しておられ、私は他の二作品とも書き慣れている秀作だと感じていた。ただ、その二作品にはしっくりこない表記がいくつかあり佳作にしていて、協議の結果は選考外となった。
冒頭で「面白い」と書いたのは、私は、テーマはもちろんだが筆力を重視し、些細な点も気になるが、長嶺委員は初めて知ることの面白さなどを優先していると思えたことだ。選考委員の視点もそれぞれなのである。
一席の「書店員の誕生日」は書店の裏側が覗けて面白かった。単に本好きのお客だった「私」が、数々の職業を経た後に書店員となり、客だった時に「本は船便で来るものですから」と言われた言葉を、書店員として船の座礁事故で痛感することになる。
二席は、“「ろんぐ」と「いらきむぬ」”という郷土の法事料理に関する作品で、母子の繋がりなどがよく書けているし、このままでは消えていく料理を記録しておく点も評価できた。ただ個人的な意見だが料理が目に浮かばなかった。重箱の中で並べる順序はあるのか、どんな味なのか…。それらも重要な要素なのでせっかく残すならもっと丁寧に描写して欲しかった。タイトルも「ロングとイラキムヌ」とした方が、ひとつの作品として扱いやすい。
佳作となった「ウチナーグチと男の子」はリズムもあるし、作者の言いたいこともよく伝わる。その子がどうなったかも書いてくれたらもっとよかったという声があった。「奇跡のラブレター」は、年金受給資格を得るために戦前の職歴の証人を探し、奇跡的に見つかった感動的な話である。ただ、「ある国」「朝令暮改」「上書き」などの言葉選びがしっくりこない。「父の手紙」も感動秘話。父への愛情の深さが感じられる。これも「後に母と出会い」「あわい」など表現が的確でない。「首里城に魅せられて」はガイドでしか書けない視点がよかったが、最後が尻切れトンボ。首里城の工事はまだ現在進行形であって、それを意識した終わり方にした方がよかったと思う。
今回は奨励賞として、中学生が書いた「星を語る人」が選ばれた。文章は稚拙で随筆というより作文に近いと感じたが、内容は面白く、今後に期待して奨励賞とした。ぜひ書き続けて欲しい。
詩部門

〔 入賞作品 〕
| 賞 | 作品名 | 作者名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 一席 沖縄県知事賞 | かなあー | うえざと りえこ | 浦添市 |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 | 島バナナ | 仲里 真哉 | 浦添市 |
| 佳作 | 恩納岳 | 田中 直次 | うるま市 |
| 佳作 | 銀杏拾い | 琴森 戀 | 南城市 |
| 佳作 | 峠 | 大城 玲子 | 大韓民国 |
| 佳作 | あなたのオーラで | 棚原 妙子 | 那覇市 |
| 奨励賞 | 自意識不足 | 邊土名 俊毅 | 浦添市 |

〔 選考委員・講評 〕

詩人・批評家。沖縄大学客員教授。
元県立高校教諭。元沖縄県史料編集室主任専門員。
1949年沖縄島南城市玉城生まれ。
日本現代詩人会会員。日本詩人クラブ会員。
詩集『岬』で第7回山之口貘賞受賞。
1985年沖縄タイムス芸術選賞奨励賞受賞。
2012年第46回沖縄タイムス芸術選賞 大賞・文学受賞。
著書に、第7詩集『絶対零度の近く』、第8詩集『ガマ』、第10詩集『群島から』、NHK生活人新書。
『ウチナーグチ(沖縄語)練習帖』、岩波新書『沖縄生活誌』、第4評論集『魂振り―琉球文化・芸術論』、第5評論集『言振り―琉球弧からの詩・文学論』など多数。
テーマと表現力
候補作は、できるだけたくさん上げたい。今年の応募総数は、三三篇であった。昨年より、三篇増えている。これは嬉しいことである。「おきなわ文学賞・詩部門」応募者が、益々拡大・発展する事を祈っている。
私の選考方法は、一つのパターンができている。まず、三三篇全部を短いコメントを付け、採点しながら一巡する。そこから、五〇点前後の作品を選んでいく。今年は、「かなあー」を始め十一篇が残った。
これらを、さらに二巡、三巡読み、コメントを加筆しながら、順位付けをしていく。まず、一席候補と二席候補の作品を選ぶ。また、佳作候補を上げる。佳作候補は、七篇が残った。これらを、事務局へ連絡する。
そして、さらに残った九篇を読み込みながら、佐藤モニカ選者とメールで意見交換をやる。おかげで、読み方がさらに多角的で深くなっていく。佳作候補を、五篇に絞り込んで選考会へ臨んだ。
選考会では、モニカ選者と交互に一篇一篇意見を交わしながら進める。まず、一席候補はうえざとりえこの「かなあー」に決まった。この詩は、ウチナーグチ(沖縄語)との「混合表現」がおもしろかった。吉増剛造や藤井貞和等も、アイヌ語や朝鮮語との混合表現を行っている。「しまくとぅば(琉球諸語)」の喪失が、アイデンティティーの危機に繋がるというテーマもいい。現況への哀感もある。欲を言えば、ウチナーグチに対して「大和口の翻訳」を付けて欲しかった。その方が、多くへ通ずる。
第二席候補は、仲里真哉の「島バナナ」が選ばれた。この作品は、お父さん、お姉ちゃん、ぼく、お母さんと登場させリズムがいい。そして、「渋い」ユーモアがある。
佳作の田中直次「恩納岳」は、惜しかった。私は、二席候補に推薦したぐらいである。詩としてのまとまりも良かった。テーマは、恩納村、恩納岳で1988年ごろに展開された都市型戦闘訓練場建設阻止闘争の歴史と経験を表現しているのだが、作者の体験とどう関わっているかが見えず、残念であった。
その他の佳作は、琴森戀「銀杏拾い」、大城玲子「峠」、棚原妙子「あなたのオーラで」だった。「銀杏拾い」はユーモアが良かった。「峠」は朝鮮語との混合表現や「従軍慰安婦問題」のテーマが評価できた。「あなたのオーラで」は強い想像力が印象に残った。学生の邊土名俊毅が「自意識不足」で、奨励賞に輝いたのは良かった。若い批判力だ。

歌人・詩人・小説家
竹柏会「心の花」所属
2010年 「サマータイム」で第21回歌壇賞次席
2011年 「マジックアワー」で第22回歌壇賞受賞
2014年 小説「ミツコさん」で第39回新沖縄文学賞受賞
2015年 小説「カーディガン」で第45回九州芸術祭文学賞最優秀賞受賞
2016年 第50回沖縄タイムス芸術選賞奨励賞受賞
2017年 詩集『サントス港』で第40回山之口貘賞受賞
2018年 歌集『夏の領域』で第62回現代歌人協会賞および第24回日本歌人クラブ新人賞受賞
2020年 詩集『世界は朝の』で第15回三好達治賞受賞(最年少受賞)
2021年 詩集『一本の樹木のように』で第17回日本詩歌句随筆評論大賞優秀賞受賞
2022年 歌集『白亜紀の風』で第18回日本詩歌句随筆評論大賞優秀賞受賞
現代歌人協会会員・日本歌人クラブ会員・日本現代詩人会会員
バラエティー豊かな作品群
第20回おきなわ文学賞詩部門、応募総数は33篇と昨年の30篇と比べ、大きな差はなかった。今回も前回同様、バラエティーに富んだ作品が目立った。
一席は「かなあー」(うえざとりえこ)に決まった。この詩はうちなーぐちとやまとぐちの混合の表現が魅力であり、自らのアイデンティティを問う作品となっている。しまくぅとばの危機は、自らのアイデンティティの危機なのである。一つつけ加えると、選考委員の私にはこのうちなーぐちを理解するのは難しかった。そこで今回は、特別に高良先生に翻訳をしていただいた。きめこまやかな翻訳により、作品を十分に理解することができた。しかし、今後こうしたうちなーぐちにて応募する際には、注釈もつけた方がよいだろう。
二席の「島(シマ)バナナ」(仲里真哉)は、沖縄の旧盆後の家の様子がありありと浮かんでくる詩だ。「島バナナ一本もいでった/バトンのように持ってった」が秀逸。一房の島バナナが、先祖から受け取ったバトンのように見事な輝きを放つ。リズムもよく、明るく、子どもから大人まで読める詩だ。佳作の「恩納(うんな)岳(だけ)」(田中直次)は一篇の詩としての存在感とまとまりがあった。また「校歌が/恩納岳の/森に吸い込まれる」の部分が美しく、惹かれた。「銀杏拾い」(琴森戀)は、祖父と自身のエピソードがモチーフだ。「支子色に輝く銀杏の実が/幾つも大地に零れ落ちている」が心に残った。最終連はない方が、余韻が残るだろう。「峠(コゲ)」(大城玲子)はアリラン(大韓民国の民謡)を重ねながら、従軍慰安婦で連れて来られた人々をテーマとした一篇。「うちの/ねえねえと/同じなのに」という言葉が胸に重く迫る。「あなたのオーラで」(棚原妙子)は、五月の早朝に偶然見掛けた中年のひとりの男から、次々と詩が紡ぎ出される。奨励賞は「自意識不足」(邊土名俊毅)。アイロニーが持ち味。もう少し掘り下げると、さらに深みが増してよさそうだ。
入賞された皆様、おめでとうございます。惜しくも入賞を逃された方もどうぞこれからも詩を書きつづけて、来年もまたおきなわ文学賞へ挑戦をしてください。皆様の作品をふたたび読ませていただくのを楽しみにしています。
短歌部門

〔 入賞作品 〕
| 賞 | 作品名 | 作者名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 一席 沖縄県知事賞 | 雨下のターミナル | 比嘉 琢磨 | 南風原町 |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 | 声の在処 | 武村 悠由 | 東京都三鷹市 |
| 佳作 | 真砂 | 武村 真子 | 東京都三鷹市 |
| 佳作 | 安里門中【贋】系図 | 安里 和幸 | 沖縄市 |
| 佳作 | 余人の夏 | 塩見 佯 | 宮古島市 |
| 佳作 | ー | 外田さし | 西原町 |
| 佳作 | その波 | 奥村 真帆 | 那覇市 |

〔 選考委員・講評 〕

1948年 沖縄県本部町に生まれる
1971年 同志社大学卒業
1995年 沖縄県歌人会入会
1996年 第18回琉球歌壇賞受賞
第2回黄金花エッセイ賞受賞
1999年 歌林の会「かりん」入会
2010年 第12回かりん力作賞受賞
2013年 第1歌集『サラートの声』刊
2014年 第48回沖縄タイムス芸術選賞奨励賞受賞
2018年 沖縄タイムス「短歌時評」執筆担当中
日本歌人クラブ会
今回は若手の作品が増えたことにより、思いがけない角度からの新鮮な発想で詠った沖縄詠を読むことができた。詩的表現へ昇華させるための技法を取り入れ、内容と韻律の響きあいを感じさせる作品もあり読み応えがあった。
一席、比嘉琢磨作の職場と個人というテーマは、ややもすると型に嵌りやすいが、作品に粗さがなく、一連として何を押し出すかという作品のまとまりが評価された。一首目と二首目の表現には職場における違和感がある。三首目に青年の自己像が描かれ、四首目には飛翔願望がある。五首目「右も左もなくてただ飛ぶ」は、二項対立が崩れてきた今の時代を想起させ、その中で平衡を保とうと思索を深めているようだ。沖縄の職業詠は少ないのでそこを起点にした独自のテーマの深まりと、現代的な展開が期待される。
二席、武村悠由作の一首目は都会での孤立感がある。二首目「ラメ入りの涙が落ちるふるさとの海の色したジンベエザメに」は魅力的だ。標準語についての三首目と、出身を詠んだ四首目はやや説明的でわかりにくかった。五首目の結び「ここではひとり」の強調によって、内なる声の響きが生まれ、新鮮で深い沖縄詠になった。
佳作、武村真子作のテーマは沖縄で、一首目に故郷を離れて初めて知った発見を詠う。二首目の南風・基地・梯梧は類型的だが、四句までの静音が美しく、結句の濁音と半濁音で不条理が伝えられ、内容と韻律が響き合った。三首目の視線、四首目の真砂、五首目の語句のかかり方などが不明瞭なので表現したいことを吟味してほしい。
佳作、安里和幸作の一首目・二首目・五首目は表現に独自性がある。死・戦争・家系をテーマにしているが、一連としてのまとまりが弱い。体言で止めると余韻が生じるので、成功している歌もあるが、多用は傷になるので要注意だ。
佳作、塩見佯作の一連は夏の終わりに心を決めかねている主体の心理的葛藤を詠う。四首目には、過ぎ去る時間のもたらす切なさがある。五首目の「熱力学第二法則」は不可逆的な現象、心の奥に余熱をもつ人だからこそ詠える法則だ。
佳作、外田さし作は実感よりも表現にウエートを置いた作風で、学校の中の場を作歌することで、思いがけない作品世界が構築されたが、二首目と四首目は曖昧で粗さが気になった。一連として何を押し出すのか、その印象が淡い。
佳作、奥村真帆作のテーマ「その波」はまだ言葉になる前の情感だろうか。言葉を胸にしまい、詩を綴ることが心に安らぎをもたらす。温もりや命をイメージさせる静かな作風は好感がもてるが、結びに粗さがある。
今年度の短歌部門は実力を感じさせる作品が多く、選ぶのが難しかった。一席の作者は昨年度の作品(佳作)より、ワンランク成長した印象があった。来年度はもっと成長した多くの作品を読めるよう期待している。

1983年沖縄県沖縄市出まれ。
2004年竹柏会「心の花」入会、佐佐木幸綱に師事。
2017年「琉球歌壇」選者に就任。
名桜大学国際学部教授。「心の花」会員、「滸」同人。
今回、短歌部門の応募は54作品で、昨年度より15作品の増加となった。応募数自体もそうだが、何より、読み応えのある作品が増えたことが嬉しい。2人の選考委員は、氏名や年齢など作者に関する情報はふせられた上で純粋に作品だけを読み、良いと思う作品を9編、事前に選出し、選考会では2人の選が重なった作品を中心に議論がなされた。上位の作品はどれも魅力的で、どれが一席になってもおかしくない激戦であったというのが、私の感想だ。
一席となった比嘉琢磨「雨下のターミナル」は職場詠を含んで人生を詠む。〈飲み会は本音をビールで流し込むオリオン瓶も汗をかいてる〉という1首目は、ビールののどごしの良さゆえに、流し込まれる「本音」が質感をもち、社会人としての実感が伝わる。「汗」に飲み会の時間(瓶に水滴がつくまでの時間)が表れており、歌が奥行きを持つ。オリオン瓶「も」だから、人も汗をかいている。その汗は、暑さというより、「本音」を押し殺すことから生まれるものだろう。3首目の〈俺よりも自立している透明なポーチが並ぶ無印を出る〉はシンプルを売りとする無印良品の商品と自分とを比べてしまう複雑な思い。シンプルなものに負ける悔しさと共に、シンプルであることへの羨望も感じられる。4首目と5首目は歌としては近く、5首連作でこのような歌が続くことは気になるものの、3首目の無印の歌がこの連作にふくらみを与えたと言えよう。
二席は武村悠由「声の在処」。県外で生活する中での沖縄への想いを詠む。〈ラメ入りの涙が落ちるふるさとの海の色したジンベエザメに〉という2首目はスマホの画面か雑誌、あるいはチラシなどを見ている場面であろう。「ラメ入りの涙」が効いている。都会の生活者としての華やかさと、「ふるさとの海の色」という素朴さの対比に、郷愁がにじむ。〈出身を明かせば酒に強くなる そういうことの連続である〉は一見するとひねりがなく、賛否が分かれる歌だろう。だが、何度か読んでいると、下句がテレビのナレーション、たとえば『ちびまる子ちゃん』のナレーションのように聞こえてくる。ナレーションのような俯瞰した詠みぶりが、ここ(県外)が自分の居場所ではないような感じを生む。「声の在処」は印象的な連作だが、1首目に問題があるように思える。2首目から5首目が現在形で詠まれる一方、1首目は「だった」と過去形である。現在との対比で過去を詠むこと自体はいいのだけれど、「だった」のはいつなのか。県外に出たばかりの頃のことか、沖縄にいた時のことか。抽象的な1首目は「だった」の幅を測れないような作りになっているように感じられる。そのことが、この連作では傷になっているのではないか。
佳作は5作品。武村真子「真砂」は基地や同化政策を詠む意欲作。基地を詠んだ2首目、デイゴを「燃える」とするのはありきたり過ぎるものの、上句は、基地があるゆえに、基地の手前で風が滞っている、とも読める。基地の前に満ちる(滞る)風がデイゴを赤くしていると捉えると面白い。伏せた視線が月光のようだという3首目の比喩も新鮮。5首目はやや難解だが、常緑樹である松の緑は、天皇の治世、寿命を言祝ぐものとして和歌では詠まれた。松を4首目の同化政策とからめて解釈することも可能だが、「貫く」と「踏みしめ」の組合せはこの歌を分かりづらくしていないだろうか。
安里和幸「安里門中【贋】系図」も印象的な連作だ。2首目、沖縄戦を生き残った人たちを「運がいい人たち」とし、自分たちはその末裔なのだとする認識。「運がいい人たち」という、ともするとぶっきらぼうな言い方が、かえって沖縄戦の悲惨さと、それを冷静に見つめる「僕」の姿勢を伝える。4首目も面白い歌ではあるが、他の4首とは異なるテイスト、テンションで、そのことが連作としての魅力を減じていないか。
塩見佯「余人の夏」の5首目は目を閉じてもくちづけがなされることもない、恋の終わりを詠んだ歌と解釈した。全体的にうまいと思わせる連作だが、胸に迫るようなインパクトには欠けるか。外田さしは、学校の怪談を詠む。軍靴の男を詠む1首目、沖縄という地で読むとより味わい深い。5首とも面白い切り口だが、淡さゆえに印象に残りづらいか。奥村真帆「その波」、1首目が美しい。2首目の下句、波が「陸でも海でもない」というのは解釈に迷う。1首目と3首目は「こと」で終わる歌。5首という短い連作に、同じ終わり方が2首あるのは傷に感じられる。
以上の入賞作7編の作者の平均年齢は約29歳だという。短歌の若い作者が増え、かつ、力をつけているということが感じられる結果である。
入賞作以外では、常盤坂もず「キソウ本能」、前原真弓「私の津波騒動」、友利正「ルビふるわたし」、北見典子「長岡花火」が印象的だった。入賞作以外は発表作にはならず、未発表作のままなので、より良い歌に推敲して、別の場で発表してもいいかもしれない。
中学や高校など、生徒の作品もあったが、個性を感じさせる歌は少なかったように感じた。そのような中では、金城孝英(中学3年)の歌が比較的、よかったと思う。
俳句部門

〔 入賞作品 〕
| 賞 | 作品名 | 作者名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 一席 沖縄県知事賞 | ― | ― | ― |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 ※順不同 | ― | 外田さし | 西原町 |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 | ― | 秋沙美 洋 | 福岡県北九州市 |
| 佳作 | 過ち | 友利 正 | 宜野湾市 |
| 佳作 | ユーフォリア | 安里 和幸 | 沖縄市 |
| 奨励賞 | 旧ぼん | 前花 澪音 | 那覇市 |
| 奨励賞 | ー | 相原 聖音 | 名護市 |
| 奨励賞 | ー | 下里和楓 | 宮古島市 |

〔 選考委員・講評 〕

結社ウエーブ/ 俳人協会・沖縄県俳句協会所属/若太陽句会代表
第九回〜十三回俳句in沖縄副実行委員長/元俳句甲子園沖縄支部支部長
句集『国際線』『新撰俳句の杜精撰アンソロジーⅠ』
ウエーブ新人賞
2005年 地元沖縄で子供達に俳句を教える活動を始める。
NHKバトル五七五学生俳句チャンピオン決定戦2010優勝
2014年 第10回おきなわ文学賞俳句部門一席
今回の大会ではほぼ全ての部門にて多数の応募があり、特に俳句部門では昨年よりも四十七作も多く、作品の水準も応募数に比例して高くなっている。
だが、おきなわ文学賞も今年で二十回目の開催となり、伝統あるこの賞に相応しい作品を選出するにあたって、今回の応募作品の中からは一席を出さない事となった。その代わり、事務局に無理を言って二席を二つに増やして貰い、奨励賞を多く選ぶ事で均衡を取らせていただいた。
奨励賞を多く出した理由は、応募者の割合として学生が多かったと言う事と、大会の目的の一つである“文化芸術の継承発展”を若手の育成と捉え、重要視した選考姿勢から来ている。
また、おきなわ文学賞を運営する沖縄県文化振興会は今年度、若手の育成を狙い、名護と宜野湾と那覇の三ヶ所でワークショップを開催した。その会では、小学生から高校生までの多くの子供達に俳句の楽しさを伝えられた様子が伺えた。そこに参加した子供達から沢山の応募があったのも奨励賞が多く選ばれた理由の一つだ。
また、前回大会にて受賞している二人の再受賞を見るに、正しく賞レースとして大会の意義が高まっているのを感じた。選考にあたっては山城初子先生とほぼ同じ作品を選んでおり、選評もほぼ同じような形であったので、個々の受賞作品についての評は先生にお任せして、こちらでは簡単に紹介させていただくのみとする。
二席の外田さしさんの作品は昨年に引き続き、沖縄らしい景を丁寧に写し取っている。が、三句目の謎の空白が気になった。前回大会の二席作品にも謎の空白があり、連続して空白のある作品が選ばれているが、山城初子先生と私の同一意見としてこの空白は無い方が良いのではないかと感じている。
同じく二席の秋沙美洋さん。慰霊の日という大きな季語に組み合わせた日常の景が含みを持っている。
佳作の友利正さん。三作の応募があり、その全てに同じくらいの魅力があった。個人的には受賞作ではない方の作品“建築の風景”が俳諧味があって好きな作品であった。
安里和幸さん。今回の受賞作で最も詩性が強い作品ではないかと思う。
以下、奨励賞等に選びきれなかった作品から抜き出した句と名前を併記して終わりたい。一句の出来としては入選作品を超えるものも多々あったので、来年もまた是非とも挑戦していただきたい。
ゴーヤーは君の生まれたうれしい日
金城美歌
夏まつりどこでもいける君となら
上地心美
血しょう板かたまりだすよ夏休み
宮城翔馬
はたけにてすいかをひとつたべつくす
金城亜竜
蝉ないてお皿洗いにとりかかる
平良結菜
人込みと夏天再起の1マイル
新里柊人
空蝉の背にほの冥し黄泉の口
棚原美知
茶柱がきき耳たてる十六夜
砂川正子
海見えるまあまあ大きいプールかな
中島求
サングラス黒い大きな窓2つ
宮里朱花
夏休みぐるぐるまわるいすのうえ
本木杏香里
バーベキューせんたくものがけむたがる
平良統進
ひよこさんぴよぴよなくよなつやすみ
宮里ななは
夏休みマトリョーシカを買ってきた
島袋聖也
ふうりんが後ろでしずかにゆれている
銘苅竹晃
たからがいいもうと名づけたウシモーモー
小川志恩
カマキリもこっそり人にあまえたい
大隅才
さがり花弟のくつ光ってる
石井千花
夏休みありとあらゆる風集め
鷹谷美幸
横たわる向日葵の花布の上
野間ちさと
カブトムシはずかしがりやのくいしんぼ
上地悠仁
にせものの羊糸で作られ手ざわりいいな
志良堂音彩
夏休みワークショップでズボンびり
平田奈瑠
カマキリは手がカマだからつなげない
岸本久虎
にせもののひまわり置いて夏休み
相原実音
ががんぼや押せども押せどもそこは壁
田原泰斗

平成13年度 那覇市世界遺産登録記念事業
那覇市世界遺産 俳句・短歌・琉歌大賞 全国コンテスト 特選受賞
第7回 「おきなわ文学賞」(2011年)随筆部門 一席
第15回 沖縄市文化の窓エッセイ賞(2012年) 佳作
第11回 「おきなわ文学賞」(2015年)俳句部門 一席
沖縄タイムス「俳句時評」執筆担当中
「俳句は、五・七・五の音数で、季語を含むかたちが基本形式ですが、季語については緩やかな使用でよいと考えます。沖縄の自然は本土の中央の歳時記どおりではありません。沖縄の歳時記もいくつもありますが、特にそのしばりからは自由で良いように思います。実際、例えば年中咲いている薔薇もあります。今詠みたいもの、事象があって、それにぴったり嵌まる季語がない場合は、特にとらわれることはなく、無季であっていいと思います。十七音を、多少はみだすとしても、詩の世界ができあがることを念じます。句材は今目の前の現実、過去未来と自由に詠んでいいと思います。
そのうえで、一句一句が独立した世界として完成度はどうか、しかも五句が揃っているかという観点、表現された世界はより内面化されているかということも大事になってきます。
留意すべきこととして、例えば沖縄の現実を表現する場合にやや類型化した傾向が見られるのは残念です。また表記では一行に棒のように書くのが基本です。分かち書きや一字開けはない方がよろしいかと思います。勿論多行形式の作家もいますが、今この段階では基本に返りたいと思います。」
昨年度の「俳句部門講評」で、私は審査にあたった側からの話を以上のようにまとめました。今回も同様の基準で進めました。
今年は昨年を上回る応募作品がありました。特筆すべきは、「おきなわ文学賞第20回記念事業」として、本木隼人さんを講師に、小中高生対象の「夏休み子どもワークショップ―つくってたのしむ俳句のせかい」が開催されたことでした。三会場で盛会裏に終わったようです。参加した子どもたちからも俳句部門への応募作品が多く寄せられたのは成果の一つといえます。したがって、応募者の年齢層も八歳から八十代後半までと幅広く、多彩な作品が揃いました。
選考過程で、上位作品については審査員の間に大きなずれはありませんでした。そのうえで慎重に討議を進めた結果、一席該当なし、二席二人、佳作二人、今回は学生以下を対象とした奨励賞に三人を決定するに至りました。
以下、各作品評です。
一席 該当作品なし
二席 外田さし
青嵐ヨナグニウマもミサイルも
ドゥタティの背中みな揺れて大夕焼
ナイターを消す 耳奥で祖父の唄
午前四時潮騒と蛾を撥ねた音
国境の風は真っ赤な扇風機
一句目の季語「青嵐」とヨマグニウマが詩情を呼ぶ。そこにまるで異物のように現れるミサイルは反詩的なものだ。相反する二つの物が示す現実への作者の違和感が伝わる。二句目「ドゥタティ」は祭りの衣装という。大勢の祭りに参加する島の人々のドゥタティに視線を集中させる。夕映えのシーンに目眩さえ感じながら感動に包まれているという作者がいる。「大夕焼け」の季語が実に生きている。まるで島が動いているさまのようでもある。この一句のダイナミックさは五句を支えるほどの存在感がある。「ドゥタティ」の方言の効果も大きい。三句目「ナイターを」の一字開きはない方が良かった。生活の中で、ふと取り戻す記憶のようなものとして、祖父の唄の声がある。心に根ざす、いわば島の魂とつながる。四句目「午前四時」は未明のリアルな、理屈を抜いた身体感覚がユニークだ。大きな潮騒の中に、蛾を撥いたかすかな音を疑いない物として捉える。五句目「国境の」の扇風機は赤い羽なのか、赤はシンボリックだ。風を詠いながら国境を前にした島の状況に不穏さを感じている。
沖縄の現実を背景に映しながら、民俗的なものもダイナミックに詠い、抒情性と批評性をも含む句世界が魅力的である。五句の全て、中心に確かな事物があるので、概念性に流れないでいる。
二席 秋沙美洋
鍋のみづ沸かして冷めて慰霊の日
夏シャツに祖母の遺せし補修跡
棺出て居間の広きや蝉時雨
祖母を焼く煙探して夏の雲
六月の風に従ひ祖母逝きぬ
五句のテーマは祖母である。過酷な沖縄戦の、その戦中、戦後を生きてきた祖母の人生を想い、温かいふところに包まれるような祖母との穏やかな生活を偲ぶ作者がいる。今、大きな時の流れの中で、この六月という沖縄の人々の祈りの満ちるこの時に、空に昇っていく祖母を見送る作者の視線。それらが五句にたっぷりと詠われている。沖縄では誰にも届く物語がここにあり、だからこそ貴重な世界が詠われている。今年は、あの対馬丸学童疎開船や、十・十空襲の悲劇から八十年目の年だった。
作品として、全体は破綻なくまとまり、構成も良い。一句目「鍋のみづ」の「沸かして冷めて」は時の経過である。祖母が生きてきた時間の伏線もあるが、決して風化してはならない「慰霊の日」も時というものに曝されもする。二句目「夏シャツ」の「補修跡」の糸と針の跡と繕う祖母の指の太い節々も目に見えるよう。三句目「棺出でて」は、実体として今そこにあった祖母の存在がまるで奪われたような喪失感と虚無感。四句目「祖母を焼く」の眩しい空。五句目「六月の」の「風に従ひ」が秀句。人は老いてゆき、歴史の流れの中に消えてゆくものでもある。そうだからこそ、悲しいし、いとおしい。
佳作 友利正
過ち
蟻地獄つながる底にすゑる核
十一時二分ガザの陰濃き長崎忌
向日葵の一計一禍鳥克蘭
ポンペイや過ちかさね星月夜
ほぐし編む地球のゆがみ毛糸玉
世界の今ある現状と、危機感が詠われる。題名「過ち」とは人類の過ちのこと。
一句目「蟻地獄」はまさに今、核の使用も辞さないという大国の言葉を連想させる。私たちは、足下の、もしかしたら崩れてしまいかねないような脆さの上にいる。二句目「十一時二分」は長崎が原爆投下を受けた時間を示して、爆撃に曝されるガザの今を繋げる。三句目「向日葵の」はロシアの侵略に防戦し続けるウクライナの様相であろうか。漢字表記の妙がある。四句目「ポンペイや」のポンペイは句群の中心で象徴的意味を持つ。ここでなぜポンペイか。火山の噴火によって一夜にして埋もれた古代都市のポンペイ。一句目の核の脅威に通底するものがある。人類の過ちがもたらす恐ろしい近未来の地球の姿を作者は想像している。地上を照らす星月夜の光景は残酷である。五句目「ほぐし編む」は一転して、祈りの句のようだ。毛糸を編むように、手仕事のようにゆがんだ地球を直していくというのだろう。毛糸玉の温みに救いがある。現実への批評意識が独特の暗喩で表現された句世界。
佳作 安里和幸
ユーフォリア
緑濃し午睡の風は湾に
片喰を踏みしだき拭く墓の破風
蝙蝠の仔ら育ちゆく陣地壕
月蝕を海蝕崖の口に喰らわせる
冬枯れの芝生を踏めば多幸感
カタカナ語のテーマ「ユーフォリア」の新鮮さと、ローカルな句材の組み合わせで不思議なインパクトのある句世界になった。一句目「緑濃し」の景は島のようでもあり、異国の半島のようでもあるが、心穏やかな物語の舞台だ。二句目「片喰を」は、かたばみを踏みつけていることのかすかな痛みに気付きながら、先祖の破風墓を掃除する。やらねばならぬことの行為の中には無意識の不本意なこともある。三句目「蝙蝠の」は、たとえば戦跡地の「陣地壕」に棲みついている蝙蝠の仔らが育っているように、どこにあっても生きものは成長し続ける。四句目「月蝕を」は興味深い。自在なイメージ力が発見した構図は多くのことを物語る。永遠に繰り返される月蝕の「蝕」。かつて、沖縄戦時の追い詰められた人々が身を投げていった 「海蝕崖」、その「蝕」。相抱くような月の形と崖であることに気づいたのだ。「喰らわせる」がやや荒々しい。五句目「冬枯れの芝生」を踏みだすのは明日への一歩だとしても「多幸感」は単純な着地点ではないかもしれない。爽涼感もある作品世界だが、過去を掬い上げながら、今の幸福感を確かなものとしながら、漠然とした不安もそこに漂っていることを感じている作者がいる。
奨励賞 前花澪音
旧ぼん
ばあばさんウンケージューシーどうですか?
中日ですあまはじならびたねとばす
ウークイでぬけたはにもウートート
お盆の三日間を自分の言葉でしっかり表現した。子どもの目線、子どもの世界の向こうに大人の忙しい盆仕事も何やら見えてくる。ウンケー、中日、ウークイにしぼって描いたのがいい。一句目はたぶんウンケーに帰ってきたお仏壇のおばあさんにジューシーの味をきく。二句目は集まった孫たちがにぎやかに、縁側に並んでスイカの種を飛ばしっこしている。三句目はウークイの日に抜けちゃった歯を(どっちの歯だろうか)、床下か屋根かに投げて、綺麗な歯が真っ直ぐ生えますようにと、ウートートと祈るのだ。何だか懐かしい郷愁さえ覚える光景に出会ったようだ。
奨励賞 相原聖音
しんぴんのえんぴつけづり夏休み
本物に見えないゾウのよこひまわり
おばあちゃん何かたべてる夏休み
ペットボトル2つなかよし夏休み
ロボットも俳句つくるの夏休み
一句目は、鉛筆削りが新品だということに気づいた。二句目、あのゾウは本物に見えない。でもその横に飾ってあるきれいなひまわりは、あれは本物だよとわかる。三句目のおばあちゃんは自分のばあちゃんかな。口が動いている。何か食べてるなと思った。四句目はペットボトルが並んでいるのを見て、人間の友だちどうしみたいと思った。五句目は俳句教室だろうか。そこに飾ってあるロボットの人形にふと聞きたいと思う。今自分も頑張っているけど、あのロボットも俳句作るのかなと。作ったらいいのにと思う。ちょっと難しいことにチャレンジしている自分にまなざしを向けているところがいい。発見して気づいてことばにすることが、俳句を作る始まりだということがよくわかる。
奨励賞 下里和楓
使わない赤青えんぴつ夏休み
炎天下ペットボトルのラベルなし
夏期こうざえんぴつのしんおれている
人形のステゴサウルス夏の雲
カラフルなビーズのかざり夏の風
一句目は、夏休みだから、いつもは授業で使う赤青えんぴつもお休みだねと思う。
二句目は、窓ぎわに置かれているペットボトルに陽が反射しているのかも知れない。ラベルがついてないのだと気が付く。三句目は夏期講座なのに、鉛筆の芯が折れちゃっているな、困ったなと思う。四句目は人形のステゴサウルスが小さく見えるなと思う。後ろの広い空の入道雲がもくもく大きいからなのかと気が付く。五句目のビーズのかざりの色とりどりがきれいだと思う。夏の風がもっときれいにと揺らしているんだろうなと思う。発見と、五句それぞれに違う季語を置く工夫をした。
応募作品は沖縄の歴史や現状を映し、自身や生活に根ざす思いを、イメージ豊かに俳句形式に表現されておりました。スケッチ風に、不条理な現実への怒りに似た感情、平和への祈り、鎮魂の思い、老いや生などなど。十七音の枠を基本に有季無季と、多様でありました。短いがゆえに、類想、類型に陥りがちなことは否めません。ですが、短いからこそ俳句文学として、より新しく、より内面化して深みのある言葉の世界を目指していきたいと思います。「沖縄には土地の力がある」というのは確かだと思います。他でもないこの土地から出てくる言葉の豊かさがあると信じます。次年度も多くの作品に出会いたいと思います。
琉歌部門

〔 入賞作品 〕
| 賞 | 作品名 | 作者名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 一席 沖縄県知事賞 | ー | 前原 武光 | うるま市 |
| 二席 沖縄県文化振興会理事長賞 | 里の志情 | 比嘉 道子 | 北中城村 |
| 佳作 ※順不同 | 想い | 島田 貞子 | 浦添市 |
| 佳作 | ー | 長嶺 八重子 | 読谷村 |
| 佳作 | 目眉美ら按司の | 安藤 うらか | 名護市 |
| 佳作 | ー | 島袋 浩大 | 那覇市 |

〔 選考委員・講評 〕

琉球大学法文学部国語国文学科卒業。沖縄県立芸術大学付属研究所所長を経て、現在名桜大学大学院特任教授。
琉球文学・文化学を専門分野として、琉球弧の祭祀や文学に関する論文を多数著す。
鎌倉芳太郎資料集の編纂で知られ、著書に『琉球の歴史と文学―おもろさうしの世界―』などがある。
今回は18 人の作者から77首の応募があった。昨年は27 人の応募者があったことからすると、9人の減少である。この減少の要因をしっかりと考えたい。
さて、今回の第1 席に選ばれたのは前原武光さんの作品であった。5 首による応募であったが、恋をテーマとする歌である。その中でも私は3 首目の「時代や変はるとも眺めゆる人の思い影宿す月の鏡」を評価した。氏の作品はいずれも安定した詠みぶりで、古格をも感じさせる。この歌の3 句目の「思い影宿す」は必ずしも分かりやすくはないが、月に恋人の面影を見るのであろう。時や国を超える人間感情の普遍性が詠われたものと受け止めた。第2 席は比嘉道子さんの作品で、「里の志情」と題された5 首である。雨水の季節から梅雨、大暑、七夕(沖縄では祖先祭祀の一つ)、そして「星晴れ」へという季節の移ろいを、今は亡き「里」(夫)への思いで繋いだ作品である。テーマを詠みきるという点ではもっとも優れていたが、一首ごとのインパクトが少し弱かったのが惜しまれる。私としては「星晴れの夜に里の星光て一期いちまでも守てたばうれ」を評価したが、それは「星晴れ」という琉球語の力に預かっている。そのような言葉を大切にしたい。
佳作には島田貞子さん、長嶺八重子さん、安藤うらかさん、島袋浩大さんの4 名の方々の作品が選ばれた。島田さんの「戦争世ぬ哀り 聞きば聞くに 現ぬ世ぬ平和 繋じいかな」が、現在の世界の情勢に対する沖縄の切実な声と評価された。長嶺さんの歌では「祝い座に響く かぎやで風三節 聴く程に深く 肝に染まて」が沖縄の風土と文化を感じさせて良かった。安藤さんの歌は「目眉美ら按司の」と題された4 首で、『おもろさうし』の14 - 986 番オモロを下敷きにしたもの。着想が斬新で、オモロの利用の仕方にはこのような方法もあるかと感心させられた。表現法としても「花や花や」(2 首目)、「今宵また今宵」(4 首目)のように、同語反復でリズムを生む試みがなされたのも面白かった。
島袋さんの作品は1 首目の「蕃花月桃 百合の花 我が庭華やかす 白の三花」がリズムもよく、また、それぞれの花の香りまでがするようである。多くの方々がさらに琉歌を学ばれ、琉歌の表現の開拓に勤しんでくれることを期待したい。

1971年 南城市知念生まれ。琉球大学人文社会学部准教授(琉球文学)。
1999年 琉球大学大学院人文社会科学研究科修了。
共編に『国立台湾大学図書館典藏琉歌大観』(国立台湾大学図書館)、『近代琉歌の基礎的研究』(勉誠出版)。
今回琉歌部門に応募してくださった方は十八名である。昨年よりも少ない応募者数であった。3首から5首を1編の作品として募集しているが、全体のまとまりを評価しつつも、必ずしも連作でなくても良いということを確認して選考が行われた。
一席には前原武光さんの作品が選ばれた。一首目は止めようにも止められない恋の思い、二首目は恋焦がれながら結ばれないことの恨めしさが歌われている。四首目は夜明けの風景、五首目は宝である美しい自然を損なってはいけないとの思いが歌われている。五首全体としての繋がりには欠けるものの、いずれの歌もリズム良くまとめられ、今回の応募作の中では突出して良いと評価された。
二席は比嘉道子さんの作品である。冒頭の三首で「雨水」「梅雨」「大暑」それぞれの季節の風景が描かれている。それに続く四首目「七夕」では亡夫への思いが、そして最後の五首目では星晴れの空に光る「里の星」に見守っていて欲しいとの願いが歌われている。春から夏、秋へと移ろう季節の中で営まれる日々の暮らし、そしてその中で変わらぬ亡夫への思いが五首全体でうまく表現されている。
佳作には今回四名の方の作品が選ばれた。島田貞子さんの作品は孫への愛情や平和な世を願う心、先祖を敬う心といった「想い」が表現され、四首目に想いを三線にのせて届けたいと詠むことでうまく全体をまとめている。長嶺八重子さんは「花」「願い」「三線」「戦争」「兄」と題された五首を組み合わせて、日々感じるさまざまな思いが表現されていた。安藤うらかさんの作品は「知花おわる目眉きよら按司」のオモロから発想を得た作品である。二首目の「花や花や」は知花花織の花が華やかに咲き乱れているようで面白く感じた。島袋浩大さんの作品は、花から花へ飛び回る働き者の蜂や、夜の庭に逆さにとまっている「かぶや」(コウモリ)など、庭の風景がユーモラスに描かれていた。
今回応募者が減っているが、日々感じる思いを沖縄語(ウチナーグチ)で表現してみたいと思っている方は他にもまだいらっしゃるのではないだろうか。だが琉歌らしい言葉遣いや表記で琉歌らしいリズムにのせて表現することを求められると、思いを琉歌にするというのはなかなかハードルが高い。琉歌らしい表現とは何か。寄せられた作品を読みながら考えさせられた選考であった。
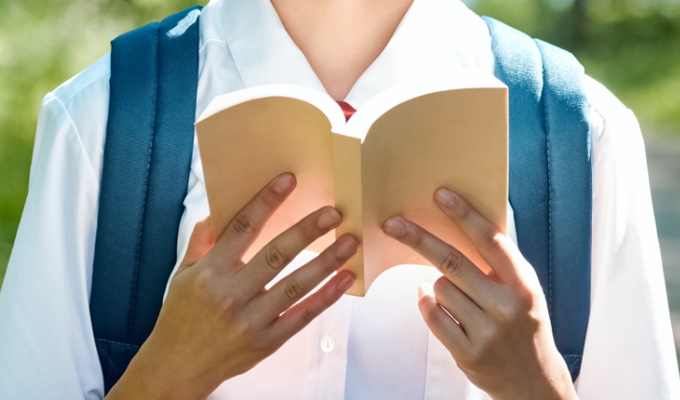
過去の入選情報はこちら
ARCHIVES


